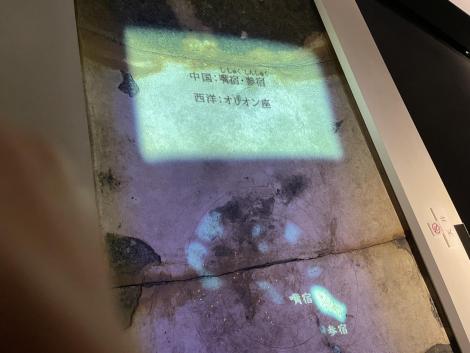飛鳥は空がおっきい
飛鳥の古墳めぐり、今日の目的地は石舞台から10分ほどの都塚古墳、それと奈文研飛鳥資料館で開催中の特別展「飛鳥池工房」を回ってみる予定です。朝出かける直前にカメラの電池の充電が殆どないことに気づき、ふたつの電池の内少なくともひとつが100%になるまで2時間ほど待って漸く出発、もう11時前。
コスモス畑の向こうに畝傍山、右手に二上山のフタコブラクダ。画面を引いて畝傍山と耳成山を一枚に、空がおっきい。
ローソン飛鳥奥山店で水を買って、石舞台方面へ右折して県道15号に入ったのは大失敗。明日香の広い谷ではなく山裾の激しいアップダウン、15分ほど大苦戦して漸く石舞台のある島庄集落に出るとかなりの賑わい。石舞台古墳は垣根で囲まれてほとんど見えません。300円の入場料を払うか、北側の高台に上がるといいのですが、先を急ぎます。
Map上に都塚古墳の近くに阪田の棚田とマーカーがあったので行ってみたのですが、案山子で知られる稲渕棚田に較べると小規模。5年前はバカ殿様がだった稲渕棚田の特大案山子、今年はやはりあの青と赤のポンデリングだったようです。1.5km先ですが、まだ間に合ったかも。
県道15号から右へ県道115号を進むと多武峰、11年も前に多武峰からこちらへ歩いて下りてきたことがあります。その時の多武峰談山神社の紅葉は実に見事でした。県道15号を手前の方に進むと吉野、大海人皇子や源義経の吉野逃避行はおそらくこの道。
飛鳥宮跡第192次調査現地説明会
自転車を停めてぐるっと回って北側から説明会場に入ると、ベニヤ板のパネルが5枚。地図や年表のパネルが2枚、写真のパネルが3枚です。この場所のGoogle Map航空写真です。飛鳥宮殿正殿跡マーカーと飛鳥宮前殿後マーカーの中間にあるあぜ道のようなところにベニヤ板5枚が立てられています。
年表部分を拡大してみたのですが、左下が前の人の帽子で隠れてしまっていて、孝徳から斉明にかけて緑色で示された都が確認できません。655年から656年の下の緑色は飛鳥川原宮で間違いないですが、その上の緑色は何なのか。下隅に「平成26年秋季特別展・特別陳列『飛鳥宮と難波宮・大津宮』図録」とあり、検索すると史跡飛鳥宮跡(飛鳥宮跡第 191 次)発掘調査成果報告の9ページに同じ年表を発見、飛鳥河辺行宮と確認できました。中大兄皇子(天智天皇)が難波宮から飛鳥に帰り一時期を過ごした行宮、どうやら稲渕棚田の手前に位置する稲渕宮殿がそれだった説が有力らしい。しかしながら孝徳天皇は飛鳥に戻ることを拒否しているので、この年表に記すべきかちょっと疑問は残ります。
午後2時になり橿考研(橿原考古学研究所)学芸員さんによる現地説明会が始まりました。今回の調査は飛鳥宮跡第192次だそうです。
飛鳥宮跡の遺構配置図と今回の調査区、広大な飛鳥宮遺構のごく限られたエリアの調査です。飛鳥宮は3時期の宮殿遺構が重複して存在、Ⅰ期遺構が舒明天皇の飛鳥岡本宮、Ⅱ期遺構が皇極天皇の飛鳥岡本宮、Ⅲ期遺構がⅢAが斉明天皇・天智天皇の後飛鳥岡本宮、ⅢBが天武天皇・持統天皇の飛鳥浄御原宮。今回の調査はⅢ期遺構の内郭(内裏)南区画の調査で上掲の掘立柱建物SB7910(正殿)の構造と規模を確認するのが目的とのことで、その目的は上述の石敷SX7916の発見などで達せられたようです。
Ⅰ期やⅡ期の遺構はⅢ期遺構の下に埋もれていて、Ⅲ期の調査が完了しないとなかなか手が付けられないらしい。ただⅢ期遺構は南北垂直方向に対し、Ⅰ期やⅡ期遺構は少し傾いているとのこと。
発掘現場から100mほど北、3月にもやってきた石敷井戸付近です。この辺りが内郭の北端になるようです。今回の調査区の内郭の南端から200mくらいあります。
飛鳥宮跡のシンボルのように立っているクスノキです。
飛鳥寺です。バイクのおっちゃんがいい感じ。
飛鳥坐神社前に出て来ました。亀形石造物を訊ねた時に教えてもらった、この手前の公衆トイレ近くで斉明天皇が造った狂心渠が確認できるはず。
飛鳥資料館
奈良文化財研究所飛鳥資料館に到着、5年ぶりです。前庭に須弥山石や亀形石造物などのレプリカが置かれ水が流れています。
エントランスホールの石人像。右側が男性で後から女性が男性を支えていると解釈されることが多いようですが、同一人物の象徴的表現という説もあるようです。
宮のうつりかわりのパネルはさっきの発掘現場の年表と比べるとかなり複雑、ビックリしたのは前期難波宮が652年から655年までのわずか3年になっていること。日本書紀では645年に孝徳天皇が難波長柄豊碕宮に遷都とあるものの宮殿が完成したのは652年、654年に孝徳天皇崩御し、655年に斉明天皇が飛鳥板蓋宮で即位(重祚)しています。難波宮の紺色部分の前後にベージュのラインがあるのは、遷都の詔勅から完成するまでの期間と、686年に焼失するまでの期間を表しているようです。
難波宮だけでなく、636年には飛鳥岡本宮、654年には飛鳥板蓋宮が焼失したことが火災アイコンで記されています。この他にも新しく作られた後飛鳥岡本宮も造られたばかりで火災にあっているらしい。狂心渠など多くの土木事業で苦しめられた民衆により放火されたとの説が有力なようです。
飛鳥宮Ⅰ期(飛鳥岡本宮)・Ⅱ期(飛鳥板蓋宮)、飛鳥宮ⅢA期(後飛鳥岡本宮)、飛鳥宮ⅢB期(飛鳥浄御原宮)の図も興味深い。左端の図からⅠ期の発掘調査は殆ど進んでいないと見て取れます。乙巳の変の現場が飛鳥板蓋宮でこのパネルの下には、蘇我入鹿の首が宙を舞っている多武峰縁起絵巻が掲げられていました。後飛鳥岡本宮と飛鳥浄御原宮の違いは天武天皇により造られたエビノコ郭が増設されているだけです。
キトラ古墳の壁画のレプリカはキトラ古墳四神の館より画像が鮮明、順に玄武、白虎、朱雀。青龍は元から判然としないので割愛。
石室天井の天文図のアニメーションです。北斗七星もオリオン座もキトラ古墳のブログで自分が描き込んだ位置が間違っていなかったと確認できました。
高松塚古墳の展示をさっと見て終末期古墳出土品の展示、七宝製亀甲形飾金具は橿考研にも展示されていたのですが、こちらの方が豪勢。
マルコ山古墳は牽牛子塚古墳の600mほど南に位置する六角墳とされる古墳、石のカラト古墳は奈良京都府県境に位置する高天原の住宅地の真ん中ある上円下方墳、いずれもユニークな墳形で訪ねてみたい古墳リストに入ってます。
地下の展示室で2つ目の目的だった特別展「古代技術の精華 飛鳥池工房」。万葉文化館に囲まれたエリアに復元されている飛鳥池工房出土品の紹介です。ちょっと簡易なジオラマは北側から飛鳥池工房の全体図。金銀製品、ガラス製品、鉄や銅製品等の工房が谷に分散していたことが分かっているようです。
二面石のレプリカ、実物は橘寺の境内で見ることができます。高松塚古墳壁画の顔出しパネル。