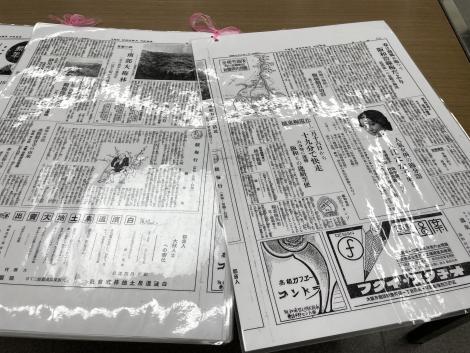摺師上町乙傘
8月17日までの「ようこそオーサカ、ようこそニッポン ―なにわ名所と物産図会―」を見たくて6月に訪ねたばかりの久保惣へ。
いつもと趣向を変えて黒背景白文字にしてみました。浮世絵を撮った下手な写真を見やすくするためです。浮世絵にはパッと見ただけでは気づかない細かい描き込みがいっぱい、それを見つけるのはとても楽しいです。スマホの場合、タップして拡大した写真をピンチアウトすると細部までよく見えるので試してみてください。以下、電車はすっ飛ばして浮世絵はこちら。
3番線のこうや号は4連1編成しかない31000系、2番線の元泉北高速5000系区間急行に乗り込みます。南海カラーへの塗装変更が発表されており、今のうちに記録しておきます。南海で先頭車貫通扉が無い車両はラピートと30000系こうや号だけ、一般車としては自分と同世代のヒゲ新こと旧1000系や丸ズームこと21000系以来ということになるはず。
なにわ名所図会と物産図会
橋本貞秀「浪速天満祭図」、画面右の大勢が踊っているのは難波橋、左の万博会場のように大勢が渡っているのは天神橋、その向こうに小さく天満橋。天神橋の向こうにお城、天神橋の向こう岸からは花火が打ち上がっています。生駒じゃなくて伊駒山、クラカリ峠、十三峠、カツラキ山と続いています。大川に目を転じるとよくぶつからないと思うくらいの舟、舟、舟。舟には描かれた人と比べると10m以上ありそうな関羽人形や清正人形も。青森のねぶた祭りのようなものではないかと。橋本貞秀は下総布佐生まれ、歌川貞秀とも号した歌川国貞門人、幕末から明治の浮世絵師。以下の作品では「浪花」なのに本作は「浪速」です。
葛飾北斎「諸国名橋奇覧 摂州天満橋」、これも天神祭を描いたもので橋の上に見物人はびっしりですが、川は貞秀に比べるとかなり寂しい。北斎は文化9年と文化14~15年頃に大坂に来ていて、北洲や北敬といった大坂の浮世絵師が北斎に弟子入りしているらしい。
一鶯斎芳梅「滑稽浪花五拾景 桃山」、わがまち上本町です。酒樽を担いだ花見の人たちが友達を見つけ手をふっているところ、酒樽のタガが外れ、こぼれた酒を物乞いが受け取っているシーンです。
上町台地東斜面は日当たりがよく果樹栽培に適していて、明治時代まで桃畑が広がっていました。今も桃谷、桃山、桃坂、桃陽といった地名が残っています。上掲の桃山学院は英国聖公会により川口外国人居留地に設立された三一小学校が前身で、1891年に筆ケ崎町に移転した際、梅の名所であったことから桃山学院と改称されています。現在の大阪赤十字病院付近です。住所には残らないものの、阪急オアシス桃坂店、UR桃坂コンフォガーデン等建物名に引き継がれています。桃陽の名は近所の人たちが丹精している桃陽ハッピーガーデンに残ります。
桃だけでなく梅でも知られていて、近鉄上本町店辺りには「梅屋敷」と呼ばれた梅園がありました。上本町Yufuraの回りにには梅の木が植えられていて今も毎年春の訪れを知らせてくれます。
もう一枚は歌川芳豊「浪花百景 うぶ湯」、筆ケ崎から近鉄と千日前通を渡った小橋公園にある産湯稲荷神社で、狐に化かされて大名行列の奴さんを気取る男の図です。坂のスロープに建つ産湯稲荷神社の様子は今もそのままです。
岳亭五岳「大阪天保山夕立の景」、岳亭春信とも号した幕末期の浮世絵師・戯作者。葛飾北斎に師事、文政から天保期にかけ数回に渡り京・大坂に滞在していたらしい。本作の構図はどうみても北斎の神奈川沖浪裏のパクリ、日本一高い富士山の代わりに日本一低い天保山がこれみよがしに大きく描かれています。神奈川沖浪裏と比べて波がさほどダイナミックでない分、山が目立ちます。江戸時代の作品のはずですが、大坂ではなく大阪になってます。ちなみに写真が歪んでいるのはガラスケースに映り込む照明を避けるため。
六花園芳雪「浪花百景 勝鬘院愛染堂」、上町台地の西側の崖に建つ勝鬘院、愛染娘さんたちによる愛染祭は大阪の夏祭りのトップバッター。自分の現住所からかつては海も見渡せたと思わせる一服ですが、描かれた山は六甲じゃなくてたぶん天保山、大きすぎます。
「下総国醤油製造之図」、積み上げられた醤油樽には「亀甲に万」。
堺刃物店を描いた「泉州境打物見世之図」、柱の向こうで刃物を打っているところからは刃物を打つ光と音が線で描き込まれています。店先には散切り頭の男性もふたりばかり。断髪令(散髪脱刀令)が発布されたのは明治4年、ちょんまげを禁止するものではなく、髪型の自由を布告したもので、この頃もまだ多くはちょんまげです。大坂と大阪、浪花と浪速、生駒と伊駒、安治川と阿治川、堺と境、あまり気にすることもなさそうです。
他にも伊豆国椿油、伊勢国鮑、若狭国鰈、摂津国伊丹酒造、大和国葛粉、和泉国桜鯛、紀伊国蜜柑、大隅国煙草など、三代歌川広重「大日本物産図会」シリーズが惜しげなく展示されていたものの割愛します。散切り頭の民衆や鉄道、洋風建築など文明開化期の世相を描いた三代歌川広重の浮世絵や錦絵は、初代歌川広重のような情緒はあまり感じさせないものの、当時の人々へ新しい時代の到来を知らしめる役割も果たしていたようです。
久保惣本館
シャガールやゴッホ、ルノアールの西洋近代美術の展示は前回と変わっていないようなので、移動します。
6月はアオモンイトトンボだったのが、今日はクロイトトンボ。
市民ギャラリー前で係の人に浮世絵ワークショップの案内を受けました。ちょっと迷って整理券をもらっておきました。実はワークショップだけじゃなく久保惣記念美術館で文楽とオペラを楽しもうというイベントがあって、入館時に案内されたものの、2時間の観劇はちょっと気が引けてパスしてしまったのですが、改めて見直してみると豊竹若太夫さんという大看板も出演と分かりちょっと後悔しています。
ワークショップというと子どもたちばかりかと思いきや、意外や大人ばかりでした。係の若い人たちが付いてくれてミスのないように丁寧に教えてくれ、さらに面映ゆくなるほどお世辞をくれます。「うなぎ」じゃなくて「ねこ」の間違いかと思いきや、やはり「うなぎ」でした。
できあがった2点、歌川国芳「猫の当て字 うなぎ」と葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」、摺師はいずれも上町乙傘(おっさん)です。意外ととても楽しかった。乙三、乙参、乙酸、乙餐、乙産、乙算…、色々考えて乙傘にしました。
青銅器以上に浮世絵にハマってきた感じがします。見ていなかった「べらぼう」も、舞台が吉原から日本橋へ変わったあたりから見始めました。中でも蔦重の妻、ていさんがお気に入り。メガネフェチです。
いずみの国歴史館
いずみの国歴史館にやってきました。宮の上公園の入口から坂道を下りたところかと思い込んでいたのですが、入口左手の建物の中と分かりました。
展示室一室だけの博物館ですが、和泉市の歴史が一気通貫で展示されています。
尼崎市歴史博物館でも大量展示されていたイイダコ壺です。イイダコ壺の数では負けている分、大型の弥生土器を大量陳列。
平安時代以降は端折って来ました。ロビーのマガジンラックに「阪和ニュース」、阪和電気鉄道の広報誌です。昭和8年2月1日号には「人気女優入江たか子来る」で浦辺粂子さんの名も。芸能人を呼んでの節分豆まきはこの当時も行われていたと分かります。葛の葉稲荷最寄りの阪和葛葉駅は現在の北信太駅、もず八幡最寄りの仁徳御陵前駅は現在の百舌鳥駅です。おばあちゃん役ばかりのイメージが強い浦辺粂子さんですが、昭和8年では30歳、かなりの美人だったようです。
「城東線電化、2月26日から」は阪和電鉄視点で「和歌山より東京、名古屋、京都、下関、神戸方面への旅は城東線阪和線経由が最短コースであるとともに安易且つ快適」とアピール。南海と熾烈な競争を繰り広げていた頃です。
昭和8年5月1日号では「春木競馬、急行停車、大増発」、春木競馬期間中急行電車を久米田駅に臨時停車する外大増発、駅から競馬場までは5人乗1台50銭の自動車便があるとのこと。昭和49年まで開催されていた春木競馬は南海線春木駅と阪和線久米田駅の中間より少し春木よりで現在は岸和田市中央公園。自分が子ども頃、南海線でも競輪だけでなく競馬開催日も急行の臨時停車や、春木行きの臨時列車も運転されていたのですが、酒臭いおっちゃんが多かったりしてあまり居心地の良くなかったので避けるようにしていた記憶があります。大掃除で見つけた古新聞みたいにキリが無いので、この辺までにしておきます。