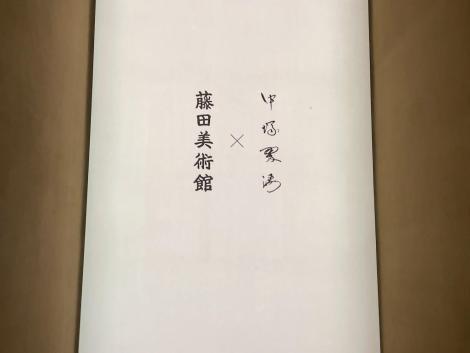国宝対決、曜変天目vs油滴天目
雨模様の週末、「国宝曜変天目茶碗を語る」という藤田美術館の座談会へ。
まずは一番奥の「誂」テーマに含まれる曜変天目へ一目散。8月から10月展示の「誂」は8月早々に訪ねているので2回目ですが、10月中に見ておかないと、来年の4月まで見ることができなくなるので今日やってきた次第。
藤田の遊
中塚翠涛「日々是好日」。「毎年同じことができるってことが幸せなんだなぁ」という樹木希林さんの映画のセリフが思い出されます。
同じ展示ケースの左下に17世紀明代の「色絵古銅三ツ人形蓋置」。元々墨を置く台だったものを、茶釜の蓋や柄杓を置くための蓋置に茶人たちが転用したそうな。表情があるかのような「日々是好日」の書と、明代の子どもたちが挨拶を交わしているかのような空間を演出。
本阿弥光悦「赤楽茶碗 銘文億」、本阿弥光悦の茶碗が見られるとは思ってもいませんでした。実にユニークなかたち、植物っぽく見えます。去年の祇園祭後祭曳き初めの日に、本阿弥光悦の足跡を辿って京の町歩きをしています。
曜変天目が展示されていなかった5月に藤田美術館を訪ねた時、樂道入(楽家3代目、ノンコウ)の黒樂茶碗を鑑賞しています。 黒樂茶碗も赤楽茶碗もろくろを使わない手捏ね。黒楽は鉄釉を何度もかけて焼成、赤楽は赤土に透明の釉薬をかけて低めの温度で焼成したものらしい。総合芸術家であった本阿弥光悦は楽家の技法を学び作陶、楽焼の派生ではあるものの、より自由奔放に美意識を昇華させており、この銘文億にそれが存分に発揮されていると感じさせます。手捏ねでよくここまで薄く仕上げたと感じ入るものの、デコボコの口縁で飲みにくそう、ストローが要るかも。
中塚翠涛「◯△□」は上掲の銘文億と並べるべく、本阿弥光悦の書を臨書し、器の形や釉薬の景色を書で表現すべく制作されたらしい。◯はコンパスで描いたような円、筆で一気にこれを書くのはハンパないです。
中塚翠涛さんと藤田美術館館長・藤田清さんの対談が公開されています。
香りを聞き名前を当てるゲーム「組香」セット、若松梅蒔絵十種香箱(江戸時代17〜18世紀)。パネルで各部品の役割やゲームのルールも詳しく説明。セットに肝心の香木は含まれておらず、香木を焚くための様々な道具と、投票するための道具一式です。
複数の香木を順に聞き(香りをかぐ)、その香りの違いを当てたり、物語や詩に結びつけて楽しむ形式の香遊び、例えるなら「香りのカルタ」や「香りの和歌合わせ」のようなもの。源氏物語の各巻にちなみ、5種類の香を組み合わせて聞き当て、香の同異を記号で表す「源氏香」などがあるとChatGTPが教えてくれました。香道の一つのようですが、全く知らなかった江戸時代の富裕層の世界、正倉院 THE SHOWで合成された蘭奢待の香りを嗅いで甘い香りが認識できただけの自分にはかなり遠い世界です。
書は「青山不動」、高い峰々と左上白い雲、香遊びから漂うお香と重ね合わせているらしい。
座右の目と同じケースに「黒漆木目地脇差拵」、柄の目貫には福助らしいフィギュア、鍔の裏側に鬼のような浮彫と羽織を着て座っている小さな動物、さらに柄頭にはウサギさん。反対側は福助の後姿。
「蔵王の銘」の末尾に置かれていた鍔に刻まれている江戸時代後期の装剣金工師・岩間政盧の作で、書のところどころに置かれたいるフィギュアもこの脇差しとセットになった打刀に取り付けられていたものと思われます。「行年七十」は通常故人に対しての表現のはずですが、ここではまだピンピンしている岩間政盧が自身のことを洒落ているようです。
座右の銘の文字の森でフィギュアたちがかくれんぼするような世界を演出すべく、新たに書き出したものと、中塚さん自身のコメントが会場のQRから読める解説にありました。後漢の崔子玉、江戸時代の岩間政盧、令和の中塚翠涛のなんとも奥深いコラボに感銘、何重にも伏線が仕込まれた映画を見るような、こういう芸のこまかさは大好きです。
座談会
座談会「国宝曜変天目茶碗を語る」が始まりました。会場は美術館ロビーの端にある座敷、その縁側の真ん中が空いていたので靴を脱がずにかぶりつき席ゲット。パネラーは藤田清館長(藤田傳三郎男爵の玄孫)とフランス近代美術が専門らしい新人学芸員さん、MCは8月にギャラリートークで曜変天目を「このコ」と呼んでいた美人学芸員さん。
パワポプレゼンの写真をアップすると分かり易いところですが、控えておいて文章で綴ります。まずは曜変天目の概要紹介、高さ6.8cm、口径12.3cm、255g、南宋時代(12〜13世紀)福建省建窯で作られたものの、制作当時の評価や使われ方や作り方、いつ日本にやってきたか、徳川家康の前は誰のもとにあったかは不明。
続いて、曜変天目の人気の秘密について。ひとつがそのサイズ感というのはナットク、これ以上大きくても小さくても宜しくないです。それと静嘉堂文庫、龍光院、藤田美術館の世界に三碗しかなく、三碗が東京、京都、大阪の三都に散在していることも魅力のひとつ。
構造色で妖しく青く光る曜変天目を、蛍光灯の下にさらした写真が紹介され、青が全く見えなくなってしまいツブツブがうっすら見えるだけの真っ黒い茶碗だったのは衝撃的。逆に光の当て方次第ではさらに青く光るようでパワポの写真は、曜変天目紹介ページの写真よりさらに青く光ってました。
最後は東洋美術美術館の将来展望。新聞社等が主催する大規模特別展はどれも輸送費や保険料で大赤字になりがち、あんなに集客しても全然儲かっていない、もっと常設展に注力すべきではないかという考えには大いに賛成です。一方、西洋美術と違って東洋美術には若い人がやってこない、という懸念は多分心配してなくてよろしいかと。高齢者はまだまだ増えます。自分も東洋美術に惹かれたのはこの年齢になってから。
「作品を彩る虫」のパネル、奈良時代から蝶が文様として工芸化したこと、平安時代の貴族が嵯峨野で鳴き声が優れた鈴虫を捕まえる「虫撰」に興じていたこと、常にまっすぐ飛ぶので勝虫と呼ばれたトンボが兜にも取り入れられるようなっとたこと、いずれも興味深い。
古芦屋糸地蒲団型釜の糸すじ文様にへばりついている虫はカイコガ、幼虫が作る糸が絹になる蚕です。野生回帰能力をなくしていて人間の管理なしには生きることのできない虫で、翅はあるものの飛翔することはできないらしい。茶釜なのに柄杓がひっかりそうな狭い口です。
芦屋は玄界灘に面した北九州市北西に位置する遠賀川河口を挟む町、芦屋釜は南北朝時代から作られているらしい。中世には下関と並ぶほど繁栄した港町であったものの、明治後は鉄道を忌避し衰退。北九州工業地帯に隣接も美しい海や縄文時代からの遺跡が残ると分かり訪ねてみたくなりました。
藤田の誂
もう一度「誂」へ。曜変天目の解説パネルにはピンクの星やハートがキラキラ、曜変推しのJKさんがまとめてくれたもののようです。座談会でも話されていた若い人たちに来てほしいという思いがここに。
曜変天目茶碗箱次第と天目台。その他の「誂」は8月の投稿を参照してください。
閉館のアナウンスが流れてきました。急いで鼻煙壷をチェック。もう3回目なので3つだけクローズアップ。いずれも5cmほどの嗅ぎタバコ用の小さな壺(明代)です。
毎月1/3ずつ展示がごっそり変更される藤田美術館と異なり、4月から11月まで7ヶ月間同じ展示の東洋陶磁美術館、ただ展示点数は藤田のたぶん10倍くらいあり、まだ見逃している掘り出し物がありそうな気はします。学芸員さんによるギャラリートークやQRコードで一点ずつ詳しく特徴や由来が掘り下げ解説されている藤田に対して、東洋陶磁ではパネルにそれぞれ特徴を一言で表すキャッチフレーズ。ただ詳しい説明はポケット学芸員というあまり使い勝手がいいとは言えない全国の美術館博物館汎用アプリに任せています。
展示ケースに肘をのせて間近で鑑賞できる棚があるのはとても快適に鑑賞でき、1点あるいは数点ずつ、鏡や白い板に載せての展示も美術品を引き立てています。